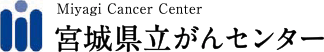令和6年度【348回~357回】
がんセンターセミナー開催記録
対象者
医学研究者及び医療従事者等
第357回
テーマ
難治性気胸の意識下手術
開催日時
令和7年3月7日(金)17:30~19:00
演者
野田 雅史(宮城県がんセンター 呼吸器外科)
概要
高齢者気胸は、重篤且つ不可逆性肺疾患の終末像で発症することが多く、一旦発症すると極めて難治性である。特に内科治療が無効で、全身状態が悪化したケースでは、内科治療、外科治療を逡巡することも少なくない。2000年初頭に、呼吸器外科領域で開始された意識下胸腔鏡手術は、これら難治性の気胸に対して、きわめて有用なアプローチと考えられている。本講演では、呼吸器外科疾患のなかで、肺癌に次いで症例数が多い気胸治療に関する治療アルゴリズムをご紹介するとともに、難治性気胸に対する意識下気胸手術の具体的事例を紹介し、最新のデジタル低圧式吸引器を用いた胸腔ドレーン管理についてもご紹介する。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第356回
テーマ
姿ハ似セガタク意ハ似セ易シ
開催日時
令和7年2月21日(金)17:30~19:00
演者
今井 啓道 先生(東北大学大学院医学系研究科 外科病態学講座 形成外科学分野 教授)
概要
形成外科は特定の臓器を持たず、対象年齢も新生児からご高齢の方まで様々です。一般的には「整容性を主目的とし外科的手技で治療を行う診療科」と定義されることもありますが、がんセンターで扱うような下咽頭癌や舌癌などの再建では整容性ではなく機能を重視した形態に再建が行われ、上記の定義は形成外科の一面を示すに過ぎないと考えています。では、我々形成外科が治療してきたものは何か?それはあくまで「姿」にこだわってきたことではないかと思っています。
私はこれまで、先天性疾患や外傷による顔の形態異常に対する治療に精力を注いできました。顔の形態異常は気道や顎、眼窩などに変形をもたらし、それは呼吸や構音、咬合・咀嚼、眼球運動などといった機能的問題を引き起こします。顔の形態異常の治療ではそれら機能的な再建も重要視されます。一方、顔の形態異常は外見の問題を引き起こします。外見の問題は本邦では軽視されることも多く、患者自身も外見の問題を気にしつつそれを医師に訴えることを躊躇しがちです。しかし、外見の問題は「姿」の違和感を生み、些細であっても、社会生活を行う上で大きな障害となり得、他の機能障害と同等の障害と言っても過言ではないと考えています。外見の問題に真摯に対応することは形成外科の使命であり、形態再現への飽くなき挑戦とともに、外科的治療のみでは治すことができない心理社会的問題にも目を向けることが求められています。本講演では、様々な先天性疾患や外傷による顔面変形に対する私の治療経験をご紹介するとともに、我々の教室で数多く手がけている頭頚部腫瘍切除に伴う顔の再建や、乳がん切除後の乳房再建術、四肢の重度外傷の再建もご紹介したいと考えています。疾患・外傷で変形した「姿」を、誰が見ても違和感ない「姿」に再現・再建することが形成外科医の理想ですが、実際は非常に困難です。今回、外見の問題で悩む患者様のために我々が行っている挑戦をご紹介することで、この問題への皆様の理解が広がることを切に願います。
私はこれまで、先天性疾患や外傷による顔の形態異常に対する治療に精力を注いできました。顔の形態異常は気道や顎、眼窩などに変形をもたらし、それは呼吸や構音、咬合・咀嚼、眼球運動などといった機能的問題を引き起こします。顔の形態異常の治療ではそれら機能的な再建も重要視されます。一方、顔の形態異常は外見の問題を引き起こします。外見の問題は本邦では軽視されることも多く、患者自身も外見の問題を気にしつつそれを医師に訴えることを躊躇しがちです。しかし、外見の問題は「姿」の違和感を生み、些細であっても、社会生活を行う上で大きな障害となり得、他の機能障害と同等の障害と言っても過言ではないと考えています。外見の問題に真摯に対応することは形成外科の使命であり、形態再現への飽くなき挑戦とともに、外科的治療のみでは治すことができない心理社会的問題にも目を向けることが求められています。本講演では、様々な先天性疾患や外傷による顔面変形に対する私の治療経験をご紹介するとともに、我々の教室で数多く手がけている頭頚部腫瘍切除に伴う顔の再建や、乳がん切除後の乳房再建術、四肢の重度外傷の再建もご紹介したいと考えています。疾患・外傷で変形した「姿」を、誰が見ても違和感ない「姿」に再現・再建することが形成外科医の理想ですが、実際は非常に困難です。今回、外見の問題で悩む患者様のために我々が行っている挑戦をご紹介することで、この問題への皆様の理解が広がることを切に願います。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第355回
テーマ
次世代人材育成と持続可能な在宅医療の実現にむけて
開催日時
令和7年2月8日(土)14:00~15:00(予定)※がんセンターフォーラムの中の特別公演です。
演者
田上 佑輔 先生(医療法人社団やまと 理事長)
概要
東日本大震災を機に、2013年宮城県登米市に在宅診療所を開設し、地域医療の課題解決に取り組んできた。都市部と地方の医師の循環型勤務体系を確立し、医師偏在の解消に寄与。ICTを活用した診療情報の統合管理や、約100項目のデータ分析による業務最適化を実現している。特にがん患者の在宅ケアにおいては、電子カルテを核とした多職種連携システムを構築し、病院との緊密な情報共有による継続的な医療提供を可能にした。本講演では、次世代の医療人材育成と持続可能な地域医療モデルの構築に向けた、デジタル技術の活用と多職種連携の実践例を紹介する。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第354回
テーマ
乳がんのゲノム医療 〜いま と これから〜
開催日時
令和7年1月17日(金)17:30~19:00
演者
多田 寛 先生(東北大学大学院医学系研究科 外科病態学講座 乳腺・内分泌外科学分野 准教授)
概要
がん遺伝子パネル検査が臨床で使えるようになって5年以上が経過しました。
乳がんでは現在5800例を超える症例に行われています。
本講演では、がん遺伝子パネル検査の結果が乳がん患者さんにどのように役立っているか、
また、リキッドバイオプシーなどの乳がんゲノム医療の新しい情報について説明したいと思います。
乳がんでは現在5800例を超える症例に行われています。
本講演では、がん遺伝子パネル検査の結果が乳がん患者さんにどのように役立っているか、
また、リキッドバイオプシーなどの乳がんゲノム医療の新しい情報について説明したいと思います。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第353回
テーマ
難治性婦人科がんに対する新たな治療開発の試み
開催日時
令和6年11月29日(金)17:30~19:00
演者
島田 宗昭 先生 (東北大学高等研究機構 未来型医療創成センター 教授)
概要
近年、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬、抗体複合薬など新たな治療開発が進み、婦人科悪性腫瘍に対する治療選択肢が増えつつある。しかしながら、新たな治療開発における「ドラック・ロス」は本邦における深刻な問題であり、難治性希少がんに対する治療開発は世界的な問題でもある。さらに、多様な背景や考えを有する患者さんに対して、新たに開発された治療選択肢の中からどのように最適な治療を選択するのか、解決すべき課題は山積みしている。 本講演では、①婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)における治療開発の試み、②東北大学クリニカルバイオバンクの構築とその活用、③適切な治療選択に向けた試み、④個別化予防に向けた取り組みについて皆様にご紹介させて頂き、ご指導を賜りたい。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第352回
テーマ
Onco-Cardiologyの現在
開催日時
令和6年11月15日(金)17:30~19:00
演者
庄司 正昭 先生 (国立がん研究センター 中央病院 循環器内科)
概要
がん治療の進歩によりがん患者の予後が向上し、がん患者やがんサバイバーで循環器疾患を発症する患者が増えてきたことから、近年、世界的に「腫瘍循環器学(Onco-Cardiology)」が注目されている。薬物療法や放射線療法などによるがん治療に伴う心血管障害は高血圧、不整脈、心不全、弁膜症、虚血性心疾患などとして発症する。がんに伴う血栓症も問題となっている。しかし、腫瘍循環器学は歴史が浅く、十分なエビデンスが不足している。ここでは腫瘍循環器における現在の問題点について共に学んでいきたい。
開催形式
第351回
テーマ
ecDNA(extrachromosomal DNA)とEBウイルスエピソームの不思議な関係
開催日時
令和6年10月18日(金)17:30~19:00
演者
神田 輝 先生(東北医科薬科大学 医学部 微生物学教室 教授)
概要
ヒト細胞核内に維持される二本鎖環状DNA分子は「エピソーム」と呼ばれる。細胞遺伝学的手法により、がん細胞にはdouble minuteというエピソーム分子が見られることは長く知られていた。double minuteは最近ecDNA(extrachromosomal DNA、染色体外DNA)という別名が与えられ、がんの悪性化に寄与する特異なDNA分子として、また新たな治療標的として国内外で研究が進んでいる。本セミナーでは、ecDNAとEBウイルスエピソームをめぐる私の経験をお話しして、本研究分野の最近の動向について議論したい。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第350回
テーマ
感染対策 up to date
開催日時
令和6年9月27日(金)17:30~19:00
演者
遠藤 史郎 先生(東北医科薬科大学 感染症学 教授)
概要
2019年12月に中国武漢で端を発した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は世界中でパンデミックを引き起こし、世界中の人々が感染対策に関心を寄せることになりました。国内において、COVID-19は5類感染症になり、感染対策にも変化が生じてきています。一方、感染症はCOVID-19のみではなく、エムポックスやオロプーシェ熱などが新興再興感染症として報告されています。感染症診療や感染対策において、情報の有無がその後に与える影響は大きいと言われています。インバウンドの増加により、今まで以上に海外で発生した感染症が日本国内に流入しやすい状況となっていることから、国内外で話題となっている感染症情報を共有したいと思います。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第349回
テーマ
みんなで行う骨転移診療
開催日時
令和6年9月6日(金)17:30~19:00
演者
柴田 浩行 先生(秋田大学大学院 医学系研究科 臨床腫瘍学講座 教授)
概要
骨転移とは血中に浸潤したがん細胞が骨髄に達し、そこに病巣が形成される病態を指す。がんは硬い骨に囲まれた環境で増殖するために、破骨細胞を誘導して骨を融解する。融解により骨は安定性を失い痛みが生じ、負荷で変形し、外力で容易に骨折する。脊椎転移は脊髄を圧迫し麻痺を生ずる。このような骨関連事象により、患者の日常生活動作は障害され、生活の質が低下する。骨転移の治療では、まず骨関連事象への対策を考える。外科治療、放射線治療、薬物療法、緩和ケア、リハビリテーション医療などの治療介入によって、利益が得られるというエビデンスが集積しつつある。複数の治療提供者が話し合い、過不足のない治療を提供する必要がある。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)※今回は演者がWebからの講義となります。
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第348回
テーマ
老化と発がんの研究
開催日時
令和6年7月19日(金)17:30~19:00
演者
浅野 直喜(宮城県がんセンター 研究所 がん幹細胞研究部)
概要
超高齢社会である本邦をはじめ、世界的にも高齢化が進み、世界は様々な課題と直面している。健康面に眼を向けると、加齢・老化は種々の臓器において発がんのリスク因子であり、老化にともなう発がん機序の解明は、健康に老いるための喫緊の課題といえる。上部消化管疾患を専門として消化器内科の診療に携わってきた演者は、これまでに胃がんの前癌病変が生じる分子生物学的機序とその中で自然免疫分子の果たす役割、老化に伴う胃発がん機序、などのテーマの元、研究を進めてきた。本セミナーでは、加齢・老化の研究に関する話題を提供しながら、自身で行ってきた加齢・老化にともなう発がん機序に関する研究をご紹介できればと思う。