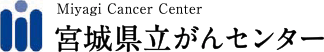平成21年度【177回~193回】
平成21年度宮城県立がんセンターセミナー
会場:宮城県立がんセンター大会議室
※医学研究者及び医療従事者を主に対象としております。
※医学研究者及び医療従事者を主に対象としております。
1.臨床試験の基盤整備:登録、論文標準化、そして倫理規定
第177回 平成21年 4月7日(火)
演者:大橋 靖雄 先生(東京大学医学系研究科公共健康医学専攻 生物統計学)
演題:臨床試験の基盤整備:登録、論文標準化、そして倫理規定
医師主導臨床試験実施に関する基盤が未成熟であったことが、わが国からのエビデンス発信不足、ひいてはがん領域のドラッグラグにつながった。近年ようやくわが国でも本格的となりつつある基盤整備の動きについて、以下をとりあげてその背景と現状を概観する。
・研究倫理と公正な結果発表の前提としての試験登録
・普及の結果、発表論文の質を向上させつつある比較試験の論文標準スタイルCONSORT宣言
・大幅に共同研究を円滑化するはずの、しかし現時点では周知されていない疫学研究の倫理規定
・今年4月から施行される臨床研究の倫理指針とその改定の意義、高度医療評価制度の位置づけと将来の方向
演者:大橋 靖雄 先生(東京大学医学系研究科公共健康医学専攻 生物統計学)
演題:臨床試験の基盤整備:登録、論文標準化、そして倫理規定
医師主導臨床試験実施に関する基盤が未成熟であったことが、わが国からのエビデンス発信不足、ひいてはがん領域のドラッグラグにつながった。近年ようやくわが国でも本格的となりつつある基盤整備の動きについて、以下をとりあげてその背景と現状を概観する。
・研究倫理と公正な結果発表の前提としての試験登録
・普及の結果、発表論文の質を向上させつつある比較試験の論文標準スタイルCONSORT宣言
・大幅に共同研究を円滑化するはずの、しかし現時点では周知されていない疫学研究の倫理規定
・今年4月から施行される臨床研究の倫理指針とその改定の意義、高度医療評価制度の位置づけと将来の方向
2.ヒト化NOGマウスの歴史と展望: ヒト疾患研究への橋渡し
第178回 平成21年5月22日(金)
演者:菅村 和夫(当センター 総長)
演題:ヒト化NOGマウスの歴史と展望: ヒト疾患研究への橋渡し
NOGマウスは東北大学が開発したX-SCIDマウスと実験動物中央研究所のNOD-SCIDマウスとを交配させて樹立した超免疫不全マウスです。種々のヒト細胞・組織が容易に生着することから、近年ヒト化マウスとして「がん」や「感染症」などヒト疾患の橋渡し研究に活用されています。本講演では、私が長年取り組んできたX-SCIDの原因遺伝子"サイトカイン共通受容体γc鎖"の発見にまつわるエピソードを先ず紹介し、引き続き、血液幹細胞移植によって樹立される免疫系ヒト化NOGマウスの研究の現状とヒトがん研究への活用応用等について紹介します。
演者:菅村 和夫(当センター 総長)
演題:ヒト化NOGマウスの歴史と展望: ヒト疾患研究への橋渡し
NOGマウスは東北大学が開発したX-SCIDマウスと実験動物中央研究所のNOD-SCIDマウスとを交配させて樹立した超免疫不全マウスです。種々のヒト細胞・組織が容易に生着することから、近年ヒト化マウスとして「がん」や「感染症」などヒト疾患の橋渡し研究に活用されています。本講演では、私が長年取り組んできたX-SCIDの原因遺伝子"サイトカイン共通受容体γc鎖"の発見にまつわるエピソードを先ず紹介し、引き続き、血液幹細胞移植によって樹立される免疫系ヒト化NOGマウスの研究の現状とヒトがん研究への活用応用等について紹介します。
3.がん細胞と免疫系の相互作用の完全理解と効果的ながん免疫療法の開発を目指して
第179回 平成21年6月3日(水)
演者:河上 裕 先生
(慶應義塾大学医学部 先端医科学研究所 細胞情報研究部門)
演題:がん細胞と免疫系の相互作用の完全理解と効果的ながん免疫療法の開発を目指して
免疫に排除されずに増殖したがん細胞に対して、免疫療法はどこまで可能か。ヒトがん抗原の同定は、生体内免疫動態の測定を可能にし、がん細胞の免疫排除に至る各過程における問題点が明らかになりつつある。がんワクチンの効果はまだ不十分であるが、培養T細胞を用いた養子免疫療法では、進行悪性黒色腫に対しても70%以上の治療効果が得られている。我々は免疫療法の改良に向けて、特に
1)がん細胞増殖に関与し、がん幹細胞にも発現するがん抗原の同定
2)内在性がん抗原に対する抗原スプレッディング誘導法の開発
3)がん細胞による免疫抑制・抵抗性の分子機構の解明と克服法の開発
に焦点を当てて研究を進めており、抗腫瘍免疫ネットワークの総合的制御を目指している。
演者:河上 裕 先生
(慶應義塾大学医学部 先端医科学研究所 細胞情報研究部門)
演題:がん細胞と免疫系の相互作用の完全理解と効果的ながん免疫療法の開発を目指して
免疫に排除されずに増殖したがん細胞に対して、免疫療法はどこまで可能か。ヒトがん抗原の同定は、生体内免疫動態の測定を可能にし、がん細胞の免疫排除に至る各過程における問題点が明らかになりつつある。がんワクチンの効果はまだ不十分であるが、培養T細胞を用いた養子免疫療法では、進行悪性黒色腫に対しても70%以上の治療効果が得られている。我々は免疫療法の改良に向けて、特に
1)がん細胞増殖に関与し、がん幹細胞にも発現するがん抗原の同定
2)内在性がん抗原に対する抗原スプレッディング誘導法の開発
3)がん細胞による免疫抑制・抵抗性の分子機構の解明と克服法の開発
に焦点を当てて研究を進めており、抗腫瘍免疫ネットワークの総合的制御を目指している。
4.ホルモン核内受容体を標的とした生活習慣病治療:PPARγとRARの新規作用の解明
第180回 平成21年6月24日(水)
演者:菅原 明(当センター 糖尿病・内分泌代謝科)
演題:ホルモン核内受容体を標的とした生活習慣病治療:PPARγとRARの新規作用の解明
チアゾリジン系薬剤をリガンドとするPPARγとレチノイン酸・レチノイドをリガンドとするレチノイン酸受容体 (RAR) は、ともにホルモン核内受容体として作用する。前者はインスリン抵抗性改善作用が、後者は分化促進作用が主たる作用として知られているが、近年これら受容体の活性化が、高血圧、動脈硬化やがんといった種々の生活習慣病に対して有効であるという報告がなされて来ている。本セミナーでは、自身のデータを中心に、これら受容体の新規作用と治療薬としての将来展望に関して概説する。
演者:菅原 明(当センター 糖尿病・内分泌代謝科)
演題:ホルモン核内受容体を標的とした生活習慣病治療:PPARγとRARの新規作用の解明
チアゾリジン系薬剤をリガンドとするPPARγとレチノイン酸・レチノイドをリガンドとするレチノイン酸受容体 (RAR) は、ともにホルモン核内受容体として作用する。前者はインスリン抵抗性改善作用が、後者は分化促進作用が主たる作用として知られているが、近年これら受容体の活性化が、高血圧、動脈硬化やがんといった種々の生活習慣病に対して有効であるという報告がなされて来ている。本セミナーでは、自身のデータを中心に、これら受容体の新規作用と治療薬としての将来展望に関して概説する。
5.Regulatory T Cell の由来など
第181回 平成21年7月10日(金)
演者:井川 洋二 先生(東京医科歯科大学大学院生命情報科学教育部 客員教授)
演題:Regulatory T Cell の由来など
生体免疫系のブレーキ役を演じるT細胞の研究は、我が国の免疫学の歴史でもある。古くは多田らのsuppressor T細胞の研究が挙げられるが、suppressor T細胞は分子レベルでの不確かさによって、現在は全く顧みられなくなっている。その後、新たに登場したのが坂口らの発見によるregulatory T細胞である。regulatory T細胞はその分子的基盤においても研究が進み、自己免疫疾患等の発症制御に深く関わっていることも明らかである。しかしながらregulatory T細胞は単一な細胞集団ではなく、免疫系を負に制御する複数の細胞集団が存在することも知られている。このような免疫系の負の調節機能を有するregulatory T細胞の起源について論じる。
演者:井川 洋二 先生(東京医科歯科大学大学院生命情報科学教育部 客員教授)
演題:Regulatory T Cell の由来など
生体免疫系のブレーキ役を演じるT細胞の研究は、我が国の免疫学の歴史でもある。古くは多田らのsuppressor T細胞の研究が挙げられるが、suppressor T細胞は分子レベルでの不確かさによって、現在は全く顧みられなくなっている。その後、新たに登場したのが坂口らの発見によるregulatory T細胞である。regulatory T細胞はその分子的基盤においても研究が進み、自己免疫疾患等の発症制御に深く関わっていることも明らかである。しかしながらregulatory T細胞は単一な細胞集団ではなく、免疫系を負に制御する複数の細胞集団が存在することも知られている。このような免疫系の負の調節機能を有するregulatory T細胞の起源について論じる。
6.酸化ストレス応答と発癌
第182回 平成21年7月15日(水)
演者:山本 雅之 先生(東北大学副学長 医学部長)
演題:酸化ストレス応答と発癌
動物は、体内に酸素を取り込んで炭水化物を燃やし、エネルギーを得ている。一方、酸素や食餌性毒物は生体にとっていたみの原因になる重大な環境ストレスである。私たちは、生体が毒物や活性酸素に暴露された際には、転写因子Nrf2により、解毒酵素・抗酸化酵素遺伝子の発現が抗酸化剤応答配列 (ARE) を介して誘導されること、一方、Nrf2活性はKeap1分子により恒常的に抑制されていることを発見した。また、毒物や活性酸素の刺激により、Nrf2はKeap1による抑制から逃れて核移行し、解毒酵素や抗酸化酵素群の遺伝子発現を活性化することを明らかにした。Nrf2およびKeap1の遺伝子欠失変異マウスの解析から、Nrf2-Keap1制御系が種々の疾患の病因に深く関与することも明らかとなった。興味深いことに、Nrf2とKeap1の点変異・機能障害は癌細胞で高率に発見される。
本研究により、外来毒物あるいは活性酸素に対する生体の適応応答メカニズムの一端が解明され、それが個体の恒常性維持において、また、疾患発症において、いかなる貢献を果たしているのかが明らかになるものと期待される。
演者:山本 雅之 先生(東北大学副学長 医学部長)
演題:酸化ストレス応答と発癌
動物は、体内に酸素を取り込んで炭水化物を燃やし、エネルギーを得ている。一方、酸素や食餌性毒物は生体にとっていたみの原因になる重大な環境ストレスである。私たちは、生体が毒物や活性酸素に暴露された際には、転写因子Nrf2により、解毒酵素・抗酸化酵素遺伝子の発現が抗酸化剤応答配列 (ARE) を介して誘導されること、一方、Nrf2活性はKeap1分子により恒常的に抑制されていることを発見した。また、毒物や活性酸素の刺激により、Nrf2はKeap1による抑制から逃れて核移行し、解毒酵素や抗酸化酵素群の遺伝子発現を活性化することを明らかにした。Nrf2およびKeap1の遺伝子欠失変異マウスの解析から、Nrf2-Keap1制御系が種々の疾患の病因に深く関与することも明らかとなった。興味深いことに、Nrf2とKeap1の点変異・機能障害は癌細胞で高率に発見される。
本研究により、外来毒物あるいは活性酸素に対する生体の適応応答メカニズムの一端が解明され、それが個体の恒常性維持において、また、疾患発症において、いかなる貢献を果たしているのかが明らかになるものと期待される。
7.医療におけるヒューマンエラーとその対策
第183回 平成21年8月4日(水)
演者:河野 龍太郎 先生(自治医科大学医学部 医療安全学)
演題:医療におけるヒューマンエラーとその対策
現在の医療システムは安全のための管理が全く不十分である。そのため、
1)エラーを誘発する要因の数や種類が極めて多く
2)エラー発生後の発見や対応などの多重防護壁が極めて弱い
ヒューマンエラーは、人間の生まれながらに持つ諸特性と人間を取り巻く広義の環境により決定された行動のうち、ある期待された範囲から逸脱したものである。エラーが発生しやすいところには、まずエラー誘発要因がある。エラー対策は第一に理にかなっていることが重要であり、「気をつけろ」「ちゃんと注意をせよ」などの人間の意識に依存した対策には限界があることを理解しなければならない。11ステップのエラー対策を具体的な事例とともに紹介する。一つでもいいので実行することが重要である。
演者:河野 龍太郎 先生(自治医科大学医学部 医療安全学)
演題:医療におけるヒューマンエラーとその対策
現在の医療システムは安全のための管理が全く不十分である。そのため、
1)エラーを誘発する要因の数や種類が極めて多く
2)エラー発生後の発見や対応などの多重防護壁が極めて弱い
ヒューマンエラーは、人間の生まれながらに持つ諸特性と人間を取り巻く広義の環境により決定された行動のうち、ある期待された範囲から逸脱したものである。エラーが発生しやすいところには、まずエラー誘発要因がある。エラー対策は第一に理にかなっていることが重要であり、「気をつけろ」「ちゃんと注意をせよ」などの人間の意識に依存した対策には限界があることを理解しなければならない。11ステップのエラー対策を具体的な事例とともに紹介する。一つでもいいので実行することが重要である。
8.がん幹細胞の可視化と血管ニッチ
第184回 平成21年9月16日(火)
演者:高倉 伸幸 先生(大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野)
演題:がん幹細胞の可視化と血管ニッチ
がん組織のがん細胞は生化学的に単一であるという従来の考え方にかわり、がん組織のがん幹細胞が自己複製を営み、がん細胞を産生して、がん組織を構築するという概念が台頭してきている。この概念は、がんの再発や、薬剤耐性の根拠を説明するうえで有用であり、がん幹細胞の発生様式や局在および細胞分裂を解析する基礎医学の必要性が提起されてきている。正常組織における幹細胞のニッチは、幹細胞の静止期状態を維持して細胞死を抑制させる領域と、幹細胞分裂を盛んにして自己と前駆細胞を産生させる血管領域に大別できる。我々は、特に血管領域にがん幹細胞が存在すれば、これらが転移に大きく関与すると予想をたて、がん幹細胞に発現する分子の単離から、これら分子をツールにがん幹細胞の可視化を試みてきた。本セミナーでは、がん幹細胞の局在について紹介するとともに、血管ニッチを形成する腫瘍周辺領域の血管の成熟化がいかにがん治療のターゲットとなるのかについて討論したい。
演者:高倉 伸幸 先生(大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野)
演題:がん幹細胞の可視化と血管ニッチ
がん組織のがん細胞は生化学的に単一であるという従来の考え方にかわり、がん組織のがん幹細胞が自己複製を営み、がん細胞を産生して、がん組織を構築するという概念が台頭してきている。この概念は、がんの再発や、薬剤耐性の根拠を説明するうえで有用であり、がん幹細胞の発生様式や局在および細胞分裂を解析する基礎医学の必要性が提起されてきている。正常組織における幹細胞のニッチは、幹細胞の静止期状態を維持して細胞死を抑制させる領域と、幹細胞分裂を盛んにして自己と前駆細胞を産生させる血管領域に大別できる。我々は、特に血管領域にがん幹細胞が存在すれば、これらが転移に大きく関与すると予想をたて、がん幹細胞に発現する分子の単離から、これら分子をツールにがん幹細胞の可視化を試みてきた。本セミナーでは、がん幹細胞の局在について紹介するとともに、血管ニッチを形成する腫瘍周辺領域の血管の成熟化がいかにがん治療のターゲットとなるのかについて討論したい。
9.臨床研究を巡る倫理についてー改正臨床研究倫理指針の解説を中心にー
第185回 平成21年9月30日(水)
演者:藤原 康弘 先生(国立がんセンター中央病院 臨床試験・治療開発部長)
演題:臨床研究を巡る倫理についてー改正臨床研究倫理指針の解説を中心にー
医療の進歩のためには臨床研究が必要であるが、被験者の福利に対する配慮が研究により得られる科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない。平成15年より導入された「 臨床研究に関する倫理指針」は、被験者の人間の尊厳及び人権を守るとともに、研究者がより円滑に臨床研究を行うことができるように定められたガイドラインである。
本セミナーでは平成21年4月より施行されている改正指針の概要を解説する。新たに研究者に加わった責務のうち、特に、健康被害に対する補償措置、臨床試験登録、実施状況報告、終了報告、教育履修義務や、旧指針より内容が具体化された重篤な有害事象報告への対応について述べる。
演者:藤原 康弘 先生(国立がんセンター中央病院 臨床試験・治療開発部長)
演題:臨床研究を巡る倫理についてー改正臨床研究倫理指針の解説を中心にー
医療の進歩のためには臨床研究が必要であるが、被験者の福利に対する配慮が研究により得られる科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない。平成15年より導入された「 臨床研究に関する倫理指針」は、被験者の人間の尊厳及び人権を守るとともに、研究者がより円滑に臨床研究を行うことができるように定められたガイドラインである。
本セミナーでは平成21年4月より施行されている改正指針の概要を解説する。新たに研究者に加わった責務のうち、特に、健康被害に対する補償措置、臨床試験登録、実施状況報告、終了報告、教育履修義務や、旧指針より内容が具体化された重篤な有害事象報告への対応について述べる。
10.ATLLに対する抗CCR4抗体による抗体療法の開発研究
第186回 平成21年10月28日(水)
演者:上田 龍三 先生(名古屋市立大学 腫瘍・免疫内科 教授/名古屋市病院局長)
演題:ATLLに対する抗CCR4抗体による抗体療法の開発研究
我々はケモカインレセプターCCR4分子に着目し、CCR4が難治性腫瘍である成人T細胞性白血病/リンパ腫 (ATLL) 、末梢性T細胞性腫瘍 (PTCL) に強く発現していることを見出し、これら造血器腫瘍の細胞起源や病態形成における本分子の役割を解析してきた。さらに、抗体療法の標的分子としての可能性について検討し、抗CCR4抗体の糖鎖を修飾(低フコース化)することにより、強力な抗体依存性細胞性障害 (ADCC) 活性と抗腫瘍効果の増強が可能であることをin vitro、in vivoの系で示し、修飾抗体の臨床応用における有用性を示唆した。これら一連の前臨床研究の成果に基づき、がんに対する抗体療法としては本邦初の臨床第I相試験を平成18年8月開始した。その結果、単独抗体療法で重篤な副作用もなくproof of concept (POC) が証明できたのみならず、期待以上の有効例が得られた。
本年6月から希少疾病用薬品 (Orphan Drug) の承認に向けた臨床第II相試験を精力的に進めている。本抗体療法の経験をもとに日本におけるTRの現状と展望についても論じたい。
演者:上田 龍三 先生(名古屋市立大学 腫瘍・免疫内科 教授/名古屋市病院局長)
演題:ATLLに対する抗CCR4抗体による抗体療法の開発研究
我々はケモカインレセプターCCR4分子に着目し、CCR4が難治性腫瘍である成人T細胞性白血病/リンパ腫 (ATLL) 、末梢性T細胞性腫瘍 (PTCL) に強く発現していることを見出し、これら造血器腫瘍の細胞起源や病態形成における本分子の役割を解析してきた。さらに、抗体療法の標的分子としての可能性について検討し、抗CCR4抗体の糖鎖を修飾(低フコース化)することにより、強力な抗体依存性細胞性障害 (ADCC) 活性と抗腫瘍効果の増強が可能であることをin vitro、in vivoの系で示し、修飾抗体の臨床応用における有用性を示唆した。これら一連の前臨床研究の成果に基づき、がんに対する抗体療法としては本邦初の臨床第I相試験を平成18年8月開始した。その結果、単独抗体療法で重篤な副作用もなくproof of concept (POC) が証明できたのみならず、期待以上の有効例が得られた。
本年6月から希少疾病用薬品 (Orphan Drug) の承認に向けた臨床第II相試験を精力的に進めている。本抗体療法の経験をもとに日本におけるTRの現状と展望についても論じたい。
11.動物発がんモデルを用いた新たな分子標的の同定
第187回 平成21年11月25日(水)
演者:野田 哲生 先生(癌研究所 研究所長)
演題:動物発がんモデルを用いた新たな分子標的の同定
近年、ヒトがんのジェネティック、エピジェネティックな異常に関して多くの情報が蓄積し、特定の種類のヒトがんに対して著功を示す分子標的薬も登場している。しかし、多くのヒトがんの中で、有効な分子標的薬が開発されているがんは、未だ限られており、現在、ヒトがんのゲノム包括的解析を通じて、新たな分子標的の同定が、盛んに行われている。一方、ジェノグラフトモデルやトランスジェニックモデルなどのヒト発がん動物モデルは、こうした新たな分子標的薬の開発における、有効性の判定やバイオマーカー探索に有用と考えられているが、実は、こうした動物モデルこそ、新たな分子標的探索のための格好な実験システムである。本講演では、遺伝学的手法を用いての、発がん動物モデルにおける、がんの発生・進展の分子機構の解析から、新規分子標的同定までのプロセスを紹介する。
演者:野田 哲生 先生(癌研究所 研究所長)
演題:動物発がんモデルを用いた新たな分子標的の同定
近年、ヒトがんのジェネティック、エピジェネティックな異常に関して多くの情報が蓄積し、特定の種類のヒトがんに対して著功を示す分子標的薬も登場している。しかし、多くのヒトがんの中で、有効な分子標的薬が開発されているがんは、未だ限られており、現在、ヒトがんのゲノム包括的解析を通じて、新たな分子標的の同定が、盛んに行われている。一方、ジェノグラフトモデルやトランスジェニックモデルなどのヒト発がん動物モデルは、こうした新たな分子標的薬の開発における、有効性の判定やバイオマーカー探索に有用と考えられているが、実は、こうした動物モデルこそ、新たな分子標的探索のための格好な実験システムである。本講演では、遺伝学的手法を用いての、発がん動物モデルにおける、がんの発生・進展の分子機構の解析から、新規分子標的同定までのプロセスを紹介する。
12.非小細胞性肺癌におけるEGFR遺伝子変異とEGFR-TKI治療

第188回 平成21年12月9日(水)
演者:前門戸 任(当センター 呼吸器内科)
演題:非小細胞性肺癌におけるEGFR遺伝子変異とEGFR-TKI治療
肺癌は日本人の年間死亡者数が5万人を超え、化学療法に抵抗性な難治性固形腫瘍の代表である。肺癌においてはこれまで幾つかの遺伝子変異が示され、発癌に関与することや治療の標的となりうることが報告されてきた。なかでも多くの悪性腫瘍で過剰発現が報告さている上皮増殖因子受容体 (EGFR) については、特に肺癌でEGFR遺伝子に変異があることが明らかとなった。非小細胞肺癌に対する初の分子標的治療剤として世界に先駆けて日本で承認された薬剤であるゲフィチニブは、そのEGFRのチロシンキナーゼ (TK) 阻害を作用機序としており、肺癌治療において重要な役割を担ってきている。このゲフィチニブの奏効例では肺癌のEGFRのTK領域において遺伝子変異が多いことが報告され、このEGFR遺伝子変異が治療効果予測因子として臨床の場で広く認識されるようになった。当施設ではこの肺癌細胞のEGFR遺伝子変異検査に早くから着手しその結果について概説するとともに、もう一つのEGFRチロシンキナーゼ阻害剤 (EGFR-TKI) であるエルロチニブが使用可能となり、二つの薬剤の違いについて当科の臨床データをもとに考察する。また、EGRF-TKI耐性患者への対策として当科と研究所で共同して行っている試みについても紹介する。
演者:前門戸 任(当センター 呼吸器内科)
演題:非小細胞性肺癌におけるEGFR遺伝子変異とEGFR-TKI治療
肺癌は日本人の年間死亡者数が5万人を超え、化学療法に抵抗性な難治性固形腫瘍の代表である。肺癌においてはこれまで幾つかの遺伝子変異が示され、発癌に関与することや治療の標的となりうることが報告されてきた。なかでも多くの悪性腫瘍で過剰発現が報告さている上皮増殖因子受容体 (EGFR) については、特に肺癌でEGFR遺伝子に変異があることが明らかとなった。非小細胞肺癌に対する初の分子標的治療剤として世界に先駆けて日本で承認された薬剤であるゲフィチニブは、そのEGFRのチロシンキナーゼ (TK) 阻害を作用機序としており、肺癌治療において重要な役割を担ってきている。このゲフィチニブの奏効例では肺癌のEGFRのTK領域において遺伝子変異が多いことが報告され、このEGFR遺伝子変異が治療効果予測因子として臨床の場で広く認識されるようになった。当施設ではこの肺癌細胞のEGFR遺伝子変異検査に早くから着手しその結果について概説するとともに、もう一つのEGFRチロシンキナーゼ阻害剤 (EGFR-TKI) であるエルロチニブが使用可能となり、二つの薬剤の違いについて当科の臨床データをもとに考察する。また、EGRF-TKI耐性患者への対策として当科と研究所で共同して行っている試みについても紹介する。
13.医療現場におけるがん患者の"良い死"について

第189回 平成22年1月20日(水)
演者:村川 康子(当センター 化学療法科)
演題:医療現場におけるがん患者の"良い死"について
がん医療の現場において、治る可能性のある患者は治癒という希望に向かって歩んで行ける。しかし、治癒を期待できない進行がん患者の場合、一時的に腫瘍縮小・症状緩和などが得られたとしても、最終地点は"死"である。このような患者に対して、我々医療従事者は疼痛の緩和と、患者が家族との良い関係を保ちながら穏やかな最後を迎えられるよう努力する。しかしこれは非常に困難であり、またある程度達成できても、患者・家族・医療従事者皆が満足感を得ることは稀である。では、末期がんの医療現場における "良い死"とは一体どの様なものであろうか。 また一般の人は自分にとっての"良い死"に対してどのようなイメージを持っているのだろうか。アンケート調査からその一端を垣間見たい。
演者:村川 康子(当センター 化学療法科)
演題:医療現場におけるがん患者の"良い死"について
がん医療の現場において、治る可能性のある患者は治癒という希望に向かって歩んで行ける。しかし、治癒を期待できない進行がん患者の場合、一時的に腫瘍縮小・症状緩和などが得られたとしても、最終地点は"死"である。このような患者に対して、我々医療従事者は疼痛の緩和と、患者が家族との良い関係を保ちながら穏やかな最後を迎えられるよう努力する。しかしこれは非常に困難であり、またある程度達成できても、患者・家族・医療従事者皆が満足感を得ることは稀である。では、末期がんの医療現場における "良い死"とは一体どの様なものであろうか。 また一般の人は自分にとっての"良い死"に対してどのようなイメージを持っているのだろうか。アンケート調査からその一端を垣間見たい。
14.肺がんの新しい原因遺伝子EML4-ALKの発見とその臨床展開
第190回 平成22年2月20日(土)
演者:間野 博行 先生(自治医科大学 ゲノム機能研究部 教授)
演題:肺がんの新しい原因遺伝子EML4-ALKの発見とその臨床展開
我々はがん臨床検体より原因遺伝子を効率よく同定する目的で、高感度レトロウィルスcDNAライブラリー構築法を新たに開発し、これを用いて肺腺がん検体から新しい融合型がん遺伝子EML4-ALKを発見することに成功した (Nature 448:561) 。これは肺がん細胞内において染色体転座が生じた結果、ALKチロシンキナーゼの酵素活性領域が微小管会合タンパクEML4のN末側半分と融合したものであり、ちょうどBCR-ABLのように極めて強力ながん化能を獲得する。EML4-ALKを肺胞上皮特異的に発現するトランスジェ ニックマウスは生後すぐに両肺に数百個の肺腺がんを発症するが、ALKキナーゼの阻害剤を投与したところこれら腫瘍は速やかに消失した (PNAS 105:19893) 。実際の肺がん症例に用いるALK阻害剤の開発が現在複数の製薬会社で進行しているが、そのうち1社は既に臨床試験を開始しておりその劇的とも言える治療効果が報告されている。我々も日本における同遺伝子陽性肺がんの検出ネットワークを開始し、患者の臨床試験参加を支援している。
以上より我々の研究の成果によって、今後世界中の何万人・何十万人もの肺がん患者の生命予後が改善されると期待される。
演者:間野 博行 先生(自治医科大学 ゲノム機能研究部 教授)
演題:肺がんの新しい原因遺伝子EML4-ALKの発見とその臨床展開
我々はがん臨床検体より原因遺伝子を効率よく同定する目的で、高感度レトロウィルスcDNAライブラリー構築法を新たに開発し、これを用いて肺腺がん検体から新しい融合型がん遺伝子EML4-ALKを発見することに成功した (Nature 448:561) 。これは肺がん細胞内において染色体転座が生じた結果、ALKチロシンキナーゼの酵素活性領域が微小管会合タンパクEML4のN末側半分と融合したものであり、ちょうどBCR-ABLのように極めて強力ながん化能を獲得する。EML4-ALKを肺胞上皮特異的に発現するトランスジェ ニックマウスは生後すぐに両肺に数百個の肺腺がんを発症するが、ALKキナーゼの阻害剤を投与したところこれら腫瘍は速やかに消失した (PNAS 105:19893) 。実際の肺がん症例に用いるALK阻害剤の開発が現在複数の製薬会社で進行しているが、そのうち1社は既に臨床試験を開始しておりその劇的とも言える治療効果が報告されている。我々も日本における同遺伝子陽性肺がんの検出ネットワークを開始し、患者の臨床試験参加を支援している。
以上より我々の研究の成果によって、今後世界中の何万人・何十万人もの肺がん患者の生命予後が改善されると期待される。
15.こんなところにも数学が!
第191回 平成22年2月20日(土)
演者:秋山 仁 先生(東海大学 教育開発研究所 所長)
演題:こんなところにも数学が!
心配性なコックさんがスープを味見するとき、大鍋一杯飲みほして苦いとか薄いとか調べていたら、客に出すスープがなくなってしまう。だから、大鍋の中のスープをかき混ぜた後、スプーン一杯を試飲するだけで全体の味をチェックするのであるが、これで十分高い信頼性が得られているのである。 このような何の変哲もないシーンの中に、実は数学が散らばっている。
植物の葉の並び、折り紙と幾何学、音楽の背後にある数学、宝くじと確率・・・と枚挙にいとまがない。特に今回の講演場所を踏まえ、がん細胞がなぜ切頭八面体に近い形をしているのかや、病院で見かける最新の機器、たとえばESWL(体外衝撃波腎結石破砕装置)、MRI(磁気共鳴映像装置)などの中に潜む数学も分かり易く紹介する。
私たちの生活に深く関わっている数学の魅力と不思議を、数学が好きじゃない大人でも楽しめるようにわかりやすく解説したい。数学ってこんなに身近でおもしろい、数学もなかなかやるなと感じていただけたら幸甚である。
演者:秋山 仁 先生(東海大学 教育開発研究所 所長)
演題:こんなところにも数学が!
心配性なコックさんがスープを味見するとき、大鍋一杯飲みほして苦いとか薄いとか調べていたら、客に出すスープがなくなってしまう。だから、大鍋の中のスープをかき混ぜた後、スプーン一杯を試飲するだけで全体の味をチェックするのであるが、これで十分高い信頼性が得られているのである。 このような何の変哲もないシーンの中に、実は数学が散らばっている。
植物の葉の並び、折り紙と幾何学、音楽の背後にある数学、宝くじと確率・・・と枚挙にいとまがない。特に今回の講演場所を踏まえ、がん細胞がなぜ切頭八面体に近い形をしているのかや、病院で見かける最新の機器、たとえばESWL(体外衝撃波腎結石破砕装置)、MRI(磁気共鳴映像装置)などの中に潜む数学も分かり易く紹介する。
私たちの生活に深く関わっている数学の魅力と不思議を、数学が好きじゃない大人でも楽しめるようにわかりやすく解説したい。数学ってこんなに身近でおもしろい、数学もなかなかやるなと感じていただけたら幸甚である。
16.角膜の再生医療

第192回 平成22年3月3日(土)
演者:西田 幸二 先生(東北大学 眼科・視覚科学分野 教授)
演題:角膜の再生医療
1990年初頭に提唱された組織工学の概念は、目的とした組織の形状に合わせて立体的に成形した人工足場に上に細胞を播種することにより、組織を構築するというものである。しかし、人工足場として用いられた生分解性ポリマーの溶解により惹起される炎症反応をいかに抑制するかが長年の課題として残されてきた。細胞シート工学はこのような人工足場を用いない革新的な次世代の組織工学技術である。
現在、角膜移植術が必要な患者は全世界で100万人以上と見積もられている。しかし、実際に角膜移植を受けている患者数は年間6万人足らずであり、多くの国で提供眼球不足が大きな問題となっている。また、現在の角膜移植医療では、他人の角膜を移植する同種移植であるので、原疾患によっては拒絶反応が大きな問題点となる。特に、アルカリ腐蝕や熱傷、Stevens-Johnson症候群などの角膜上皮疾患では、拒絶反応のため移植成績が不良である。このような現在の移植医療が抱える問題点を抜本的に解決するため、患者自身の細胞を用いた再生医療の開発が待望されてきた。我々は温度応答性培養皿に基づく細胞シート工学を角膜上皮再生に応用し、独自の自家培養角膜上皮細胞シート移植法を世界ではじめて開発した。低温度処置のみで細胞シートを培養皿から剥離回収することにより、細胞間あるいは細胞接着タンパクを維持したまま、培養細胞を一枚の連続したシートとして培養皿から剥離することが可能になり、移植した細胞シートの生着率が著しく向上した。我々はさらに患者自身の口腔粘膜上皮幹細胞を角膜上皮幹細胞の代わりに細胞源として用いる方法をはじめて開発した。動物への移植実験に成功後、2004年より臨床応用を開始し、現在まで極めて良好な成績を得ている。
本講演では、我々が開発してきた角膜再生医療の基礎研究と臨床成績を紹介したい。
演者:西田 幸二 先生(東北大学 眼科・視覚科学分野 教授)
演題:角膜の再生医療
1990年初頭に提唱された組織工学の概念は、目的とした組織の形状に合わせて立体的に成形した人工足場に上に細胞を播種することにより、組織を構築するというものである。しかし、人工足場として用いられた生分解性ポリマーの溶解により惹起される炎症反応をいかに抑制するかが長年の課題として残されてきた。細胞シート工学はこのような人工足場を用いない革新的な次世代の組織工学技術である。
現在、角膜移植術が必要な患者は全世界で100万人以上と見積もられている。しかし、実際に角膜移植を受けている患者数は年間6万人足らずであり、多くの国で提供眼球不足が大きな問題となっている。また、現在の角膜移植医療では、他人の角膜を移植する同種移植であるので、原疾患によっては拒絶反応が大きな問題点となる。特に、アルカリ腐蝕や熱傷、Stevens-Johnson症候群などの角膜上皮疾患では、拒絶反応のため移植成績が不良である。このような現在の移植医療が抱える問題点を抜本的に解決するため、患者自身の細胞を用いた再生医療の開発が待望されてきた。我々は温度応答性培養皿に基づく細胞シート工学を角膜上皮再生に応用し、独自の自家培養角膜上皮細胞シート移植法を世界ではじめて開発した。低温度処置のみで細胞シートを培養皿から剥離回収することにより、細胞間あるいは細胞接着タンパクを維持したまま、培養細胞を一枚の連続したシートとして培養皿から剥離することが可能になり、移植した細胞シートの生着率が著しく向上した。我々はさらに患者自身の口腔粘膜上皮幹細胞を角膜上皮幹細胞の代わりに細胞源として用いる方法をはじめて開発した。動物への移植実験に成功後、2004年より臨床応用を開始し、現在まで極めて良好な成績を得ている。
本講演では、我々が開発してきた角膜再生医療の基礎研究と臨床成績を紹介したい。
17.がんにおけるシアリダーゼ異常とがん診療への応用

第193回 平成22年3月17日(土)
演者:宮城 妙子(当センター 研究所 生化学部)
演題:がんにおけるシアリダーゼ異常とがん診療への応用
細胞のがん化に伴うシアル酸異常は浸潤や転移などのがんの悪性形質と深く関連することが旧来から指摘されてきた。事実、シアル酸は臨床診断で頻用される腫瘍マーカーに多く含まれている。その意義と機構の解明および臨床応用をめざして、シアル酸の脱離によってその調節を行うシアリダーゼについて研究を進めてきた。これまでヒトではシアリダーゼ4種 (NEU1-4) が同定されているが、がん化で互いに異なった変化を遂げることを見いだした。
本講演では、主に、多くのがんで異常亢進を示す形質膜局在シアリダーゼNEU3のがんにおける役割とそれを標的とするがん治療の可能性について最近の成果を紹介したい。
演者:宮城 妙子(当センター 研究所 生化学部)
演題:がんにおけるシアリダーゼ異常とがん診療への応用
細胞のがん化に伴うシアル酸異常は浸潤や転移などのがんの悪性形質と深く関連することが旧来から指摘されてきた。事実、シアル酸は臨床診断で頻用される腫瘍マーカーに多く含まれている。その意義と機構の解明および臨床応用をめざして、シアル酸の脱離によってその調節を行うシアリダーゼについて研究を進めてきた。これまでヒトではシアリダーゼ4種 (NEU1-4) が同定されているが、がん化で互いに異なった変化を遂げることを見いだした。
本講演では、主に、多くのがんで異常亢進を示す形質膜局在シアリダーゼNEU3のがんにおける役割とそれを標的とするがん治療の可能性について最近の成果を紹介したい。