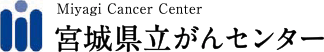平成28年度【271回~283回】
平成28年度宮城県立がんセンターセミナー
会場:宮城県立がんセンター大会議室
※医学研究者及び医療従事者を主に対象としております。
※医学研究者及び医療従事者を主に対象としております。
1.術後回復促進のためのエッセンス
第271回 平成28年6月3日(金)時間:18時00分-19時30分
演者:宮田 剛 先生(岩手県立中央病院 副院長)
演題:術後回復促進のためのエッセンス
外科手術後の合併症を減らして身体的回復を速め、早期に日常生活に戻れるようにすることは周術期管理に関与するすべての医療スタッフに共通した願いです。2005年にERAS (Enhanced Recovery After Surgery) という上記の主旨に沿う周術期ケアバンドルが提唱され、これを導入する施設も増えてきました。このERASとは一体何なのか、導入に際して何が問題となっていて、どうしていくのが良いのか、日本外科代謝栄養学会の周術期管理ワーキンググループとしての見解についてご紹介します。
演者:宮田 剛 先生(岩手県立中央病院 副院長)
演題:術後回復促進のためのエッセンス
外科手術後の合併症を減らして身体的回復を速め、早期に日常生活に戻れるようにすることは周術期管理に関与するすべての医療スタッフに共通した願いです。2005年にERAS (Enhanced Recovery After Surgery) という上記の主旨に沿う周術期ケアバンドルが提唱され、これを導入する施設も増えてきました。このERASとは一体何なのか、導入に際して何が問題となっていて、どうしていくのが良いのか、日本外科代謝栄養学会の周術期管理ワーキンググループとしての見解についてご紹介します。
2.ゲノム編集技術による胃がん由来EBウイルス株の単離と解析
第272回 平成28年6月10日(金)時間:17時30分-19時00分
演者:神田 剛 先生(東北医科薬科大学医学部微生物学教室 教授)
演題:ゲノム編集技術による胃がん由来EBウイルス株の単離と解析
次世代シークエンス技術の導入により、ヒト腫瘍ウイルスであるEBウイルス株の多様性と病原性との関連が注目されています。今回、ゲノム編集技術 (CRISPR/Cas9) を応用して、潜伏感染細胞からEBウイルスゲノムDNA (約175キロベース) を直接クローン化できる新しい技術を開発しました。世界初の成果として、胃がん由来EBウイルスゲノムDNAのクローン化、全塩基配列決定、感染性ウイルスの再構成による機能解析の結果についてお話しします。
演者:神田 剛 先生(東北医科薬科大学医学部微生物学教室 教授)
演題:ゲノム編集技術による胃がん由来EBウイルス株の単離と解析
次世代シークエンス技術の導入により、ヒト腫瘍ウイルスであるEBウイルス株の多様性と病原性との関連が注目されています。今回、ゲノム編集技術 (CRISPR/Cas9) を応用して、潜伏感染細胞からEBウイルスゲノムDNA (約175キロベース) を直接クローン化できる新しい技術を開発しました。世界初の成果として、胃がん由来EBウイルスゲノムDNAのクローン化、全塩基配列決定、感染性ウイルスの再構成による機能解析の結果についてお話しします。
3.生活習慣病と知らぬ間に?進行する循環器疾患
第273回 平成28年7月1日(金)時間:17時30分-19時00分
演者:加藤 浩(当センター 循環器内科)
演題:生活習慣病と知らぬ間に?進行する循環器疾患
若いつもりでいても動脈硬化は、すでに10代後半から始まってます。特に、高血圧症、脂質異常症、糖尿病は、自覚症状がなくとも知らず知らずのうちに病状を進行させるため、サイレントキラーとも呼ばれ、喫煙と合わせて動脈硬化の4大危険因子とされています。本セミナーでは、それぞれの生活習慣病が、動脈硬化にどのように関与しているのか?お話させていただきます。後半では、生活習慣病を有する虚血性心疾患の実例を提示しながら最近の虚血性心疾患の治療について、概説します。
演者:加藤 浩(当センター 循環器内科)
演題:生活習慣病と知らぬ間に?進行する循環器疾患
若いつもりでいても動脈硬化は、すでに10代後半から始まってます。特に、高血圧症、脂質異常症、糖尿病は、自覚症状がなくとも知らず知らずのうちに病状を進行させるため、サイレントキラーとも呼ばれ、喫煙と合わせて動脈硬化の4大危険因子とされています。本セミナーでは、それぞれの生活習慣病が、動脈硬化にどのように関与しているのか?お話させていただきます。後半では、生活習慣病を有する虚血性心疾患の実例を提示しながら最近の虚血性心疾患の治療について、概説します。
4.これからの医療理念『ICF(生活機能分類)』の基礎
第274回 平成28年7月22日(火)時間:17時30分-19時00分
演者:山室 誠 先生(岡部医院仙台院長 東北大学名誉教授)
演題:これからの医療理念『ICF(生活機能分類)』の基礎
国際生活機能分類 (ICF) は2001年にWHO総会で採択された「健康の構成要素に関する分類」で介護・福祉では知られているが、医療分野では、一 部の看護師を除き、殆どの医師にはなじみが薄い言葉である。それは国際障害分類 (ICIHD) の改定版として出された経過にもあるが、超高齢社会 を迎え、高齢者やがん患者など緩和ケアを必要する人々も、「すべての人は障害者と言う過程を経て亡くなる」という視点から、脚光を浴びるようになった。特に行政はICFを「すべての人に関係する分類」と位置付け、健康・疾病・介護・および保険などの分野での共通言語化を目指している。そこで今回はICFの基礎的概念 (可能ならコード化まで) について話す。
演者:山室 誠 先生(岡部医院仙台院長 東北大学名誉教授)
演題:これからの医療理念『ICF(生活機能分類)』の基礎
国際生活機能分類 (ICF) は2001年にWHO総会で採択された「健康の構成要素に関する分類」で介護・福祉では知られているが、医療分野では、一 部の看護師を除き、殆どの医師にはなじみが薄い言葉である。それは国際障害分類 (ICIHD) の改定版として出された経過にもあるが、超高齢社会 を迎え、高齢者やがん患者など緩和ケアを必要する人々も、「すべての人は障害者と言う過程を経て亡くなる」という視点から、脚光を浴びるようになった。特に行政はICFを「すべての人に関係する分類」と位置付け、健康・疾病・介護・および保険などの分野での共通言語化を目指している。そこで今回はICFの基礎的概念 (可能ならコード化まで) について話す。
5.全国がん登録と院内がん登録ー がん登録の仕組みと利用 ー
第275回 平成28年9月9日(金)時間:17時30分-19時00分
演者:西本 寛 先生(国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター センター長)
演題:全国がん登録と院内がん登録-がん登録の仕組みと利用-
平成28年1月から「がん登録推進法」が施行され、全ての病院において「全国がん登録」が開始され、 同時に、拠点病院を中心に実施されてきた「院内がん登録」も法的位置づけが与えられた。この2つのがん登録を進めていくことにより、がん対策 の情報基盤が確立し、分析に基づくがん対策の立案が可能となることが期待されている。一方、医療機関の側からは、これらの成果が、がん診療にどのような影響をするか、また、どのような利用ができるのかが、不明瞭な部分も多い。具体的なデータを提示しつつ、2つのがん登録の仕組みを 通して、がん登録情報の利用の実際をお話しします。
演者:西本 寛 先生(国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター センター長)
演題:全国がん登録と院内がん登録-がん登録の仕組みと利用-
平成28年1月から「がん登録推進法」が施行され、全ての病院において「全国がん登録」が開始され、 同時に、拠点病院を中心に実施されてきた「院内がん登録」も法的位置づけが与えられた。この2つのがん登録を進めていくことにより、がん対策 の情報基盤が確立し、分析に基づくがん対策の立案が可能となることが期待されている。一方、医療機関の側からは、これらの成果が、がん診療にどのような影響をするか、また、どのような利用ができるのかが、不明瞭な部分も多い。具体的なデータを提示しつつ、2つのがん登録の仕組みを 通して、がん登録情報の利用の実際をお話しします。
6.iPS細胞を利用するがん幹細胞研究とその将来性
第276回 平成28年9月23日(金)時間:17時30分-19時00分
演者:妹尾 昌治 先生(岡山大学大学大学院自然科学研究科 教授)
演題:iPS細胞を利用するがん幹細胞研究とその将来性
iPS細胞を利用するがん幹細胞研究とその将来性内容:iPS細胞は再生医療にとって最も重要な材料として期待されている。しかし、その多能性は、再生医療における危惧とは裏腹に、がん細胞を生み出す材料としても有効と考えられる。私たちはこれまでに、がん細胞株の培養上清を用いてiPS細胞を培養するとがん幹細胞が得られることを 示してきた。これは、患者の腫瘍細胞・組織に依らず、がん幹細胞が生じる過程の解析、がん幹細胞の性質の解析やマーカー探索、がん幹細胞に有効な薬剤のスクリーニング、PDXに替わる動物病態モデル作成などこれまでに無かったがん研究の新材料となる可能性を示している。本セミナーでは、これまでの研究で得られた知見と将来性について紹介させていただきたい。
演者:妹尾 昌治 先生(岡山大学大学大学院自然科学研究科 教授)
演題:iPS細胞を利用するがん幹細胞研究とその将来性
iPS細胞を利用するがん幹細胞研究とその将来性内容:iPS細胞は再生医療にとって最も重要な材料として期待されている。しかし、その多能性は、再生医療における危惧とは裏腹に、がん細胞を生み出す材料としても有効と考えられる。私たちはこれまでに、がん細胞株の培養上清を用いてiPS細胞を培養するとがん幹細胞が得られることを 示してきた。これは、患者の腫瘍細胞・組織に依らず、がん幹細胞が生じる過程の解析、がん幹細胞の性質の解析やマーカー探索、がん幹細胞に有効な薬剤のスクリーニング、PDXに替わる動物病態モデル作成などこれまでに無かったがん研究の新材料となる可能性を示している。本セミナーでは、これまでの研究で得られた知見と将来性について紹介させていただきたい。
7.オートファジーの異常と肝腫瘍:オートファジー欠損マウスからわかったこと
第277回 平成28年9月30日(金)時間:17時30分-19時00分
演者:小松 雅明 先生(新潟大学医歯学系 分子遺伝学 教授)
演題:オートファジーの異常と肝腫瘍:オートファジー欠損マウスからわかったこと
オートファジーは、オートファゴソーム内に取り込まれた細胞内タンパク質をアミノ酸にまで分解する非選択的な大規模分解系である。このシステムは、栄養飢餓により激しく誘導されることから、自己タンパク質の分解によるアミノ酸供給を介した究極の生存戦略と考えられる。 一方、我々は、栄養豊富な状態においてもオートファジーは恒常的に起こっていること、この恒常的オートファジーによるタンパク質・オルガネラ品質管理が、特に老廃物除去が生存に必須と考えられる非分裂細胞において重要なことを明らかにしてきた。また、オートファジーに選択的タンパク質識別機構があることも判明した。 本講演では、オートファジーの生理機能および疾患、特に肝細胞がんとの関連を紹介したい。
演者:小松 雅明 先生(新潟大学医歯学系 分子遺伝学 教授)
演題:オートファジーの異常と肝腫瘍:オートファジー欠損マウスからわかったこと
オートファジーは、オートファゴソーム内に取り込まれた細胞内タンパク質をアミノ酸にまで分解する非選択的な大規模分解系である。このシステムは、栄養飢餓により激しく誘導されることから、自己タンパク質の分解によるアミノ酸供給を介した究極の生存戦略と考えられる。 一方、我々は、栄養豊富な状態においてもオートファジーは恒常的に起こっていること、この恒常的オートファジーによるタンパク質・オルガネラ品質管理が、特に老廃物除去が生存に必須と考えられる非分裂細胞において重要なことを明らかにしてきた。また、オートファジーに選択的タンパク質識別機構があることも判明した。 本講演では、オートファジーの生理機能および疾患、特に肝細胞がんとの関連を紹介したい。
8.T細胞のテロメレース発現とDNAメチル化
第278回 平成28年11月18日(金)時間:17時30分-19時00分
演者:中村 正孝 先生(東京医科歯科大学シニアURA・特任教授)
演題:T細胞のテロメレース発現とDNAメチル化
T細胞は、正常でテロメレースを発現する例外的な体細胞である。テロメレース遺伝子 (hTERT) の発現は免疫機能維持に必要だが、細胞の不死化に関わるため厳密な発現制御が求められる。我々は、転写因子KLF2のプロモーターへの結合がhTERTの転写を抑制することを見出した。プロモーター のDNAメチル化はKLF2の結合を阻止し、hTERTが発現する。患者末梢血ATL細胞は、正常T細胞と同様にhTERTプロモーターのDNAメチル化がなく、HTLV-1感染細胞株でメチル化がみられるのとは対照的であった。
演者:中村 正孝 先生(東京医科歯科大学シニアURA・特任教授)
演題:T細胞のテロメレース発現とDNAメチル化
T細胞は、正常でテロメレースを発現する例外的な体細胞である。テロメレース遺伝子 (hTERT) の発現は免疫機能維持に必要だが、細胞の不死化に関わるため厳密な発現制御が求められる。我々は、転写因子KLF2のプロモーターへの結合がhTERTの転写を抑制することを見出した。プロモーター のDNAメチル化はKLF2の結合を阻止し、hTERTが発現する。患者末梢血ATL細胞は、正常T細胞と同様にhTERTプロモーターのDNAメチル化がなく、HTLV-1感染細胞株でメチル化がみられるのとは対照的であった。
9.陽子線治療の現状と保険収載に向けた今後の展望
第279回 平成29年1月13日(金)時間:17時30分-19時00分
演者:和田 仁 先生
(一般財団法人 脳神経疾患研究所附属 南東北がん陽子線治療センター陽子線治療研究所所長)
演題:陽子線治療の現状と保険収載に向けた今後の展望
T細胞は、正常でテロメレースを発現する例外的な体細胞である。テロメレース遺伝子 (hTERT) の発現は免疫機能維持に必要だが、細胞の不死化に関わるため厳密な発現制御が求められる。我々は、転写因子KLF2のプロモーターへの結合がhTERTの転写を抑制することを見出した。プロモーターのDNAメチル化はKLF2の結合を阻止し、hTERTが発現する。患者末梢血ATL細胞は、正常T細胞と同様にhTERTプロモーターのDNAメチル化がなく、HTLV-1感染細胞株でメチル化がみられるのとは対照的であった。
演者:和田 仁 先生
(一般財団法人 脳神経疾患研究所附属 南東北がん陽子線治療センター陽子線治療研究所所長)
演題:陽子線治療の現状と保険収載に向けた今後の展望
T細胞は、正常でテロメレースを発現する例外的な体細胞である。テロメレース遺伝子 (hTERT) の発現は免疫機能維持に必要だが、細胞の不死化に関わるため厳密な発現制御が求められる。我々は、転写因子KLF2のプロモーターへの結合がhTERTの転写を抑制することを見出した。プロモーターのDNAメチル化はKLF2の結合を阻止し、hTERTが発現する。患者末梢血ATL細胞は、正常T細胞と同様にhTERTプロモーターのDNAメチル化がなく、HTLV-1感染細胞株でメチル化がみられるのとは対照的であった。
10.VEGF-VEGF受容体シグナル系の腫瘍血管新生における役割
第280回 平成29年2月18日(土)時間:15時00分ー16時00分
演者:澁谷 正史 先生(上武大学学長 / 医学生理学研究所所長)
演題:VEGF-VEGF受容体シグナル系の腫瘍血管新生における役割
がんの増殖・転移に血管系が重要であることは以前より示唆されていたが、25年ほど前までは分子レベルの血管調節機構はほとんど不明であった。1989年に血管新生因子・透過性因子であるVEGF-Aの遺伝子が単離され、1990年に我々は新規受容体キナーゼ遺伝子 Fms-like tyrosine kinase (Flt-1) を報告し、Flt-1が最初のVEGF受容体 (VEGFR-1) であることが示された。その後、VEGFファミリー 5種、VEGFRファミリー3種が血管・ リンパ菅新生の基本的な調節機構であることが明らかとなった。多くの腫瘍はVEGF-Aを発現し、その程度は低酸素下に促進される。VEGF-Aは VEGFR-1 (Flt-1) とVEGFR-2 (KDR) と結合するが、VEGFR-2は強いキナーゼ活性をもち、直接の血管内皮増殖にはVEGFR-2シグナルが主に関与する。一方、VEGFR-1は胎生期にはVEGF-Aをトラップすることにより血管新生を抑制的に調節するが、成熟期にはマクロファージ等に発現してそれらの腫瘍への遊走・ケモカイン産生等を刺激することにより腫瘍血管新生と転移を促進させる。VEGF-VEGFRシグナルを標的にした抗体・低分子抗がん剤はすでに複数開発され、がん患者の生存期間を延長することが示されて、多くの固形がんに広く臨床応用されている。しかし、残された問題も多い。
今回のセミナーでは、VEGF系の詳細と、今後の課題などをお話ししたい。
演者:澁谷 正史 先生(上武大学学長 / 医学生理学研究所所長)
演題:VEGF-VEGF受容体シグナル系の腫瘍血管新生における役割
がんの増殖・転移に血管系が重要であることは以前より示唆されていたが、25年ほど前までは分子レベルの血管調節機構はほとんど不明であった。1989年に血管新生因子・透過性因子であるVEGF-Aの遺伝子が単離され、1990年に我々は新規受容体キナーゼ遺伝子 Fms-like tyrosine kinase (Flt-1) を報告し、Flt-1が最初のVEGF受容体 (VEGFR-1) であることが示された。その後、VEGFファミリー 5種、VEGFRファミリー3種が血管・ リンパ菅新生の基本的な調節機構であることが明らかとなった。多くの腫瘍はVEGF-Aを発現し、その程度は低酸素下に促進される。VEGF-Aは VEGFR-1 (Flt-1) とVEGFR-2 (KDR) と結合するが、VEGFR-2は強いキナーゼ活性をもち、直接の血管内皮増殖にはVEGFR-2シグナルが主に関与する。一方、VEGFR-1は胎生期にはVEGF-Aをトラップすることにより血管新生を抑制的に調節するが、成熟期にはマクロファージ等に発現してそれらの腫瘍への遊走・ケモカイン産生等を刺激することにより腫瘍血管新生と転移を促進させる。VEGF-VEGFRシグナルを標的にした抗体・低分子抗がん剤はすでに複数開発され、がん患者の生存期間を延長することが示されて、多くの固形がんに広く臨床応用されている。しかし、残された問題も多い。
今回のセミナーでは、VEGF系の詳細と、今後の課題などをお話ししたい。
11.癌進展に関与する分子機序解明を目指して
第281回 平成29年3月2日(木)時間:17時30分ー19時00分
演者:佐藤 賢一(当センター研究所 がん幹細胞研究部)
演題:癌進展に関与する分子機序解明を目指して
遺伝子の変異や欠失の蓄積によって発生した癌は、運動能を獲得して周辺臓器に浸潤・転移するようになり悪性度を増強させて進展していきす。本研究部では、この浸潤・転移に関与する分子機序を解明することが、癌の悪性度を予測するマーカーの発見や進行癌の治療標的の同定に結び付くと考え研究を行ってきました。このセミナーでは、non-coding RNAのHotairをはじめとした様々な分子が癌進展にどのように関与しているの か、研究部開設から6年間取り組んできた結果をお話しします。
演者:佐藤 賢一(当センター研究所 がん幹細胞研究部)
演題:癌進展に関与する分子機序解明を目指して
遺伝子の変異や欠失の蓄積によって発生した癌は、運動能を獲得して周辺臓器に浸潤・転移するようになり悪性度を増強させて進展していきす。本研究部では、この浸潤・転移に関与する分子機序を解明することが、癌の悪性度を予測するマーカーの発見や進行癌の治療標的の同定に結び付くと考え研究を行ってきました。このセミナーでは、non-coding RNAのHotairをはじめとした様々な分子が癌進展にどのように関与しているの か、研究部開設から6年間取り組んできた結果をお話しします。
12.X線高精度放射線治療の発展、これまでとこれからー強度変調放射線治療を中心にー
第282回 平成29年3月3日(金)時間:17時30分ー19時00分
演者:藤本 圭介(当センター 放射線治療科)
演題:X線高精度放射線治療の発展、これまでとこれからー強度変調放射線治療を中心にー
1895年にX線が発見されて間もない頃から、放射線によるがん治療が研究されてきましたが、特に1990年代以後、IT技術と相俟った機械工学の進歩に伴い、様々な高精度放射線治療が開発され、多くの新たな知見が生まれています。本院においては2013年集学治療棟の完成時に新たな放射線治療装置"トモセラピー"が導入されて以後、多数の患者に強度変調放射線治療(IMRT)を提供しています。
本セミナーでは、これまでどのような観点で高精度放射線治療が開発されてきているのか整理すると同時に、IMRTの実地臨床の概説や現時点で未 解決の問題に対する新たな研究の方向性に関しても紹介いたします。
演者:藤本 圭介(当センター 放射線治療科)
演題:X線高精度放射線治療の発展、これまでとこれからー強度変調放射線治療を中心にー
1895年にX線が発見されて間もない頃から、放射線によるがん治療が研究されてきましたが、特に1990年代以後、IT技術と相俟った機械工学の進歩に伴い、様々な高精度放射線治療が開発され、多くの新たな知見が生まれています。本院においては2013年集学治療棟の完成時に新たな放射線治療装置"トモセラピー"が導入されて以後、多数の患者に強度変調放射線治療(IMRT)を提供しています。
本セミナーでは、これまでどのような観点で高精度放射線治療が開発されてきているのか整理すると同時に、IMRTの実地臨床の概説や現時点で未 解決の問題に対する新たな研究の方向性に関しても紹介いたします。
13.肺癌診療の進歩と共に歩んだこの11年
第283回 平成29年3月8日(水)時間:17時30分ー19時00分
演者:前門戸 任(当センター呼吸器内科 診療科長)
演題:肺癌診療の進歩と共に歩んだこの11年
宮城県立がんセンターに赴任して11年になります。その間、肺癌診療は目まぐるしく進歩しました。EGFR遺伝子変異肺癌の診断治療に始まり、ALK肺癌が発見され、病理部の協力のもとALK免疫組織染色を東北各地から無償検査を行う取組を行いました。陽性となった患者には劇的に効く薬剤が適応となり福音となったことと思います。最近では、免疫チェックポイント阻害剤が上市され院内スタッフの協力のもといち早く投与体制の整備を行いました。これまで転移性肺がんに治癒は期待できませんでしたが、この免疫チェックポイント阻害剤治療によって治癒を期待できるところまで治療が進歩しました。スタッフに恵まれた充実した11年を振り返ります。
演者:前門戸 任(当センター呼吸器内科 診療科長)
演題:肺癌診療の進歩と共に歩んだこの11年
宮城県立がんセンターに赴任して11年になります。その間、肺癌診療は目まぐるしく進歩しました。EGFR遺伝子変異肺癌の診断治療に始まり、ALK肺癌が発見され、病理部の協力のもとALK免疫組織染色を東北各地から無償検査を行う取組を行いました。陽性となった患者には劇的に効く薬剤が適応となり福音となったことと思います。最近では、免疫チェックポイント阻害剤が上市され院内スタッフの協力のもといち早く投与体制の整備を行いました。これまで転移性肺がんに治癒は期待できませんでしたが、この免疫チェックポイント阻害剤治療によって治癒を期待できるところまで治療が進歩しました。スタッフに恵まれた充実した11年を振り返ります。