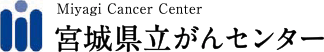令和4年度【327回~339回】
がんセンターセミナー開催記録
対象者
医学研究者及び医療従事者等
第339回
テーマ
がんセンター30年の歩みとこれから
開催日時
2023年3月10日(金)17:30~19:00
演者
荒井 陽一(宮城県立病院機構理事長、宮城県立がんセンター総長)
概要
がんセンターは1993年、成人病センターから名称変更し、あたらしく研究所と共に開設された。2011年には法人化を経て現在にいたる。自律性、機動性、柔軟性を最大限に発揮しながら、常に時代のニーズを先取りして先進的医療を提供できる体制を着実に整備してきた。がんセンター30年の歩みを振り返りながら、がんセンターのミッションと今後を展望したい。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第338回
テーマ
がんロコモ ~運動器マネジメントが変えるがん診療~
開催日時
2023年2月4日(土)15:00~16:00
テーマ
河野 博隆(帝京大学医学部整形外科学講座主任教授)
概要
平成30年に日本整形外科学会が提唱した「がんロコモ」は日本のがん診療に大きな影響を与えました。がん患者の運動器マネジメントに注目が集まり、令和4年の骨転移診療ガイドライン改訂には整形外科から多くの作成委員が関わるなど、がん診療における整形外科のプレゼンスが着実に高まりつつあることを実感しています。
我が国の骨・軟部腫瘍医は、これまで「運動器領域の腫瘍」に取り組み、このorthopaedic oncology領域で国際的にも大きな成果を上げてきました。 世界随一の超高齢社会である我が国において、これからは、骨・軟部腫瘍医だけでなく、整形外科医全員が「がんロコモ」に代表される「がん患者の運動器診療」を対象にしたonco-orthopaedicsという新たな領域にも取り組むことにより、さらに運動器診療が、がん診療を通じて社会全体に貢献できることを示せると確信しています。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第337回
テーマ
放射線治療科20年の変遷
開催日時
2023年1月27日(金)17:30~19:00
演者
久保園 正樹(がんセンター放射線治療科診療科長)
概要
1999年に医師となり来月で48歳になります。人生のちょうど半分を医師として過ごし、初期研修を除くそのほとんどを放射線治療医として過ごしました。
20年前と放射線治療、実業務がどう変わったかを徒然なるままにまとめてみました。若干の当院の症例提示もあります。研究的な内容では無いですしあまりメッセージ性の高いスライドではないので気楽に聞いていただければと思います。
20年前と放射線治療、実業務がどう変わったかを徒然なるままにまとめてみました。若干の当院の症例提示もあります。研究的な内容では無いですしあまりメッセージ性の高いスライドではないので気楽に聞いていただければと思います。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第336回
テーマ
腫瘍循環器学の最近の話題 ~放射線関連心血管障害などにもふれて~
開催日時
2023年1月20日(金)17:30~19:00
演者
志賀 太郎(がん研究会有明病院 院長補佐、総合診療部 部長、腫瘍循環器・循環器内科 部長)
概要
腫瘍循環器学が関わる疾患分野は広く、心機能障害・心不全、心膜疾患、血栓塞栓症、血圧異常、肺高血圧症、刺激伝導系異常など大変幅広い。特にがん治療関連心筋障害 (CTRCD; Cancer Therapeutics Related Cardiac Dysfunction)、血栓塞栓症は臨床上の注目度が高い。そして、放射線関連心血管障害(RACD; Radiation Associated Cardiovascular Diseases)も重要な課題である。放射線治療(RT)の技術革新によりRACDのリスクは減少していると予想するが、がんサバイバーが増加傾向にある昨今、そして、高齢化により循環器疾患既往を持つRT患者の増加も予想され、今後もRACDを診療する機会は無くなることはない。本セミナーでは腫瘍循環器学の最近の話題についてRACDも含めてお話をさせて頂きたいと考えている。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
参加登録はこちらから
参加登録はこちらから
第335回
テーマ
膵がんに挑む! ~我々は膵がんを克服できるのか?~
開催日時
2023年1月13日(金)17:30~19:00
演者
虻江 誠(がんセンター消化器内科診療科長)
概要
膵がんは年間37,000人を超える患者さんが亡くなっており,部位別死亡数においては第4位で年々増加傾向にある.膵がんは早期発見が困難で診断時には既に切除不能であることが多いため,その生存率は極めて低い状況となっており,医学が進歩した現在においても代表的な難治がんという位置づけは変わっていない.膵がんに打ち勝つにはどうすれば良いか,どうすれば早期発見ができるのか,そして予後を延長できる方法はあるかなど,膵がん診療で直面している課題に対して,最近の動向を踏まえながら診断および治療の面からアプローチする。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
第334回
テーマ
やってはいけない無計画切除
開催日時
2022年12月9日(金)17:30~19:00
演者
鈴木 一史(宮城県立がんセンター整形外科診療科長)
概要
悪性軟部腫瘍に対して十分に術前の画像評価や鑑別診断を行わずに切除する無計画切除が問題となっている。本セミナーでは無計画切除がなぜ問題なのか、そしてもし無計画切除を行ってしまうとどのような問題を生じるのかを症例を供覧しつつ解説する。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
第333回
テーマ
妊孕性温存療法とは
開催日時
2022年12月2日(金)17:30~19:00
演者
海法 道子(宮城県立がんセンター婦人科診療科長)
概要
若年のがん患者にとってがん治療は最優先であるものの、がん克服後の後遺症や自分の将来すなわち学業・仕事・生活・家族に関しての不安や悩みは多岐にわたる。治療による生殖機能への影響・不妊の問題もその一つである。がん治療による生殖機能へのリスクに関する情報を早期に患者へ提供し、生殖機能温存を希望する・温存可能な病状の患者対して妊孕性温存療法を提案することが重要である。宮城県で行われているがん・生殖医療の現状や、婦人科がんに対して取り組んでいる妊孕性温存療法について解説する。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
第332回
テーマ
神経内分泌がんに対する新たな代謝標的治療のプロトタイプ
開催日時
2022年11月18日(金)17:30~19:00
演者
田沼 延公(宮城県立がんセンター研究所がん薬物療法研究部部長)
概要
私たちは、がんの代謝特性を解明し、新たな治療標的として開拓することを目標に研究をすすめています(1-3)。一環として、以前、小細胞肺がん(SCLC)のPKM1 依存”という性質を報告しました(4)。この研究を発展させ、最近、動物実験にて高い治療効果を示す新たな“代謝ターゲット治療”を開発しました。この治療は、SCLC以外にも、再発前立腺がんを筆頭に、神経内分泌分化を呈する種々のがんに対して効果を期待できそうです。一連の取り組みを紹介します。
参考文献
1.Morita M, Cancer Sci. ‘21
2.Kikuchi N, BBRC, ‘20
3.Kudo K, FEBS J, ‘20
4.Morita M, Cancer Cell ‘18
参考文献
1.Morita M, Cancer Sci. ‘21
2.Kikuchi N, BBRC, ‘20
3.Kudo K, FEBS J, ‘20
4.Morita M, Cancer Cell ‘18
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
第331回
テーマ
せん妄における最近の知見と当院で可能な対応
開催日時
2022年11月11日(金)17:30~19:00
演者
山下 元康(宮城県立がんセンター精神腫瘍科診療科長)
概要
せん妄は「見向きもされない」症状のひとつともいわれていたが、論文数はこの10~20年間で増加しつつあり、令和2年からせん妄ハイリスクケア加算が診療報酬に加わるなど、実臨床での関心も高まっている。本セミナーではせん妄に関する最近の知見を当院での実情も鑑みながら幾つか紹介する予定である。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
第330回
テーマ
乳がん検診の歴史的経緯と有効性評価
開催日時
2022年10月28日(金)17:30~19:00
演者
大貫 幸二(宮城県立がんセンター乳腺外科診療科長)
概要
日本における対策型乳がん検診は1987年に視触診法で開始されましたが、当時欧米では複数のRCTで死亡率減少効果が証明されていたマンモグラフィ検診が行われていました。日本でも精度管理システムを整えて2000年からマンモグラフィ検診が導入されましたが、欧米ではマンモグラフィ検診に死亡率減少効果がないとして、2014年頃にはマンモグラフィ検診の中止を勧告する団体もでてきました。しかし、現在はincidence-based mortalityの手法を用いた研究によりマンモグラフィ検診の有効性が確認されています。乳癌は自覚症状が出てもすぐに治療を始めれば比較的予後が良いため、self-selection biasなどが紛れ込みやすいことが知られています。本セミナーでは、論文の批判的吟味も行いながら、乳がん検診の経緯と問題点について解説します。
開催形式
ハイブリッド形式(大会議室・オンライン開催)
第329回
テーマ
ステロイドホルモン研究における組織学的アプローチ法
開催日時
2022年10月7日(金)17:30~19:00
演者
鈴木 貴(東北大学大学院医学系研究科病理検査学分野)
概要
ステロイドホルモンの動態や病態生理を正しく理解するためには、生化学的解析とともに組織学的な視点が欠かせない。ステロイドホルモンは血中や組織液中を移動するため、組織学的な解析は容易ではない。しかし目的に則して形態学的解析を工夫し、それに生化学的手法を組み合わせることで、ステロイドホルモンの本質がより深く見えてくる。そこで本セミナーではステロイドホルモンを組織学的に解析する際の基本的な考え方や、代表的な解析法を説明する。このような組織学的アプローチが、他の領域の研究においても何らかのヒントになれば幸いである。
開催形式
オンライン開催
第328回
テーマ
腫瘍循環器学におけるアンメット・メディカル・ニーズとリアル・ワールド・エビデンス
開催日時
令和4年9月2日(金) 17:30 ~ 18:45
演者
佐瀬 一洋(順天堂大学大学院医学研究科 臨床薬理学)
概要
超高齢社会における罹患者数増加と医療の進歩による治療成績向上により、がんサバイバー数が急増しつつある。
腫瘍循環器学は、ハイリスク患者の治療完遂支援やハイリスク治療後のフォローなど、患者アウトカム向上を共通目標とする学際領域の多職種連携である。
しかしながら、診療ガイドラインの基盤となるエビデンスは不足しており、アンメット・メディカル・ニーズに対する基礎・臨床・疫学研究の必要性が示されている。
本セミナーでは、現場におけるチーム医療や地域医療連携を国や学会レベルからの教育・診療・研究支援につなげるために、米国FDAが提唱するリアル・ワールド・エビデンスという新しい研究手法を含め、議論を深めたい。
腫瘍循環器学は、ハイリスク患者の治療完遂支援やハイリスク治療後のフォローなど、患者アウトカム向上を共通目標とする学際領域の多職種連携である。
しかしながら、診療ガイドラインの基盤となるエビデンスは不足しており、アンメット・メディカル・ニーズに対する基礎・臨床・疫学研究の必要性が示されている。
本セミナーでは、現場におけるチーム医療や地域医療連携を国や学会レベルからの教育・診療・研究支援につなげるために、米国FDAが提唱するリアル・ワールド・エビデンスという新しい研究手法を含め、議論を深めたい。
第327回
テーマ
がんにおける染色体不安定性の原因とその影響
開催日時
令和4年7月22日(金) 17:30 ~ 19:00
演者
田中 耕三 (東北大学加齢医学研究所)
概要
大部分のがん細胞では染色体の数や構造の異常(異数性)が見られ、その背景には細胞分裂の際に染色体の不均等な分配が高頻度で起こる状態(染色体不安定性)が存在する。近年がんにおける染色体不安定性の研究が精力的に進められ、染色体不安定性をひき起こす様々な原因が明らかになってきている。一方染色体不安定性がどのようにがん化やがんの進行と関連するのかという点は、長らく不明であったものの、最近徐々に明らかになりつつある。
本セミナーでは、当研究室のデータを交えながら、がんにおいて染色体不安定性がどのように生じ、それががんにどのような影響を及ぼすのかを概説する。
本セミナーでは、当研究室のデータを交えながら、がんにおいて染色体不安定性がどのように生じ、それががんにどのような影響を及ぼすのかを概説する。