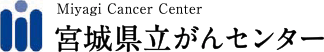呼吸器外科
診療科紹介
呼吸器外科は、主に肺がんを中心とした肺・縦隔の悪性腫瘍の手術を担当します。胸部の外科は胸腔鏡を用いた低侵襲手術が中心となっており、ロボット胸腔鏡手術を含めて当科の手術症例は95%以上が胸腔鏡を用いて行われています。また、今日の肺がん治療は手術、抗がん剤、放射線を組み合わせた、いわゆる「集学的治療」をそれぞれの患者さんの病状に合わせて行うことが基本となっています。こうした集学的治療では、手術だけでなく手術前の導入化学療法や、手術後の補助化学療法、再発してしまった患者さんに対する抗がん剤治療や放射線治療、さらにはがんによる多彩な症状を和らげる緩和ケアなども含まれます。当科でも関連する学会がまとめている「肺がん診療ガイドライン」に即して、呼吸器内科や放射線治療科、緩和ケア内科などと連携しながら、個々の患者さんにとって最も適切と考えられる治療を提供しています。