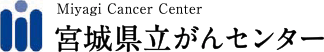形成外科
診療科紹介
形成外科は「形」と「きず」を診て治すところです。がんセンターでは多くの手術が行われていますが、たとえば口腔がんによって顎の骨が切除されると、何らかの方法で顎の骨を再建しないと食べたり話したりすることに大きな障害が残ります。また乳がんで乳房が全摘されると、衣服の上からは分からなくても、温泉に行く気になれないなど本人にとっては精神的な障害になることもあります。
手術だけでなくがんの治療では放射線や薬物治療によってもその副作用として治りにくく、きず (皮膚壊死・潰瘍・瘻孔など) を生じることもあり、またその後の傷跡 (瘢痕・ケロイド) による見栄え (整容) の悪さも「きず」による障害と言っていいでしょう。
こういったがん治療によって生じた異常な「形」や「きず」を、できるだけ機能的にも整容的にも治しているのが形成外科です。
手術だけでなくがんの治療では放射線や薬物治療によってもその副作用として治りにくく、きず (皮膚壊死・潰瘍・瘻孔など) を生じることもあり、またその後の傷跡 (瘢痕・ケロイド) による見栄え (整容) の悪さも「きず」による障害と言っていいでしょう。
こういったがん治療によって生じた異常な「形」や「きず」を、できるだけ機能的にも整容的にも治しているのが形成外科です。