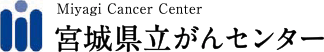整形外科
診療科紹介
当科では骨に発生する骨腫瘍と筋肉、神経、血管、脂肪などの軟部組織に発生する軟部腫瘍を主に診療し、関連診療科・関連部署と連携し、手術、リハビリテーション、化学療法、放射線療法、緩和治療を行っています。また、炎症、感染症などの腫瘍と紛らわしい疾患の診断や、がんの治療に伴う骨粗鬆症などの運動器障害にも積極的に対応しています。
近年、がん自体やがんの治療によって骨や関節・筋肉・神経などの体を動かす運動器が障害されて歩行などの移動が難しくなる「がんロコモ」が問題となっており、がん患者さんにおいても、日常生活において、健常者と同じような活動ができるように、手術、リハビリテーションを含めた治療を積極的に行っております。
近年、がん自体やがんの治療によって骨や関節・筋肉・神経などの体を動かす運動器が障害されて歩行などの移動が難しくなる「がんロコモ」が問題となっており、がん患者さんにおいても、日常生活において、健常者と同じような活動ができるように、手術、リハビリテーションを含めた治療を積極的に行っております。